就業規則・各種規定の作成
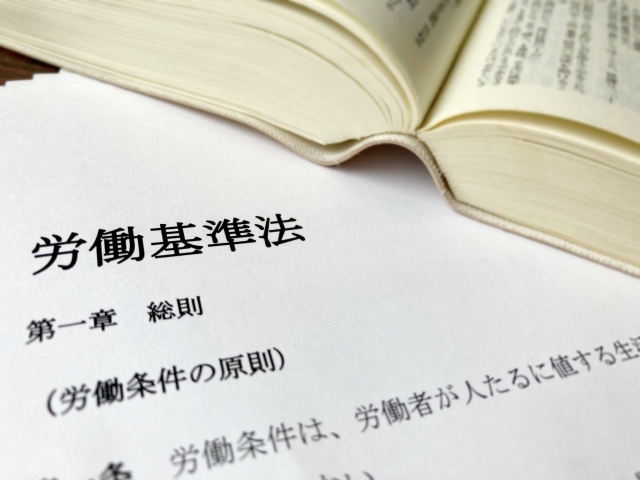
就業規則は、企業運営の要となる重要な文書であり、法令遵守と従業員との信頼関係構築に欠かせないものです。当事務所では、新規顧問契約時に無料の就業規則診断をご提供し、現状の課題を明確にした上で最適な改善策をご提案いたします。
就業規則についてご存知ですか?
①就業規則の作成義務について
- 労働基準法第89条に基づき、常時10人以上の労働者を使用する事業所には、就業規則の作成が義務付けられています。
- この「10人以上」には、正社員だけでなくパートタイムやアルバイト従業員も含まれます。
②就業規則の法的効力
就業規則は単なる社内ルールではなく、以下の条件を満たす場合に労働契約の内容となります:
- 合理的な労働条件が定められていること
労働基準法や関連法令に準拠した内容であることが求められます。 - 従業員に適切に周知されていること
従業員がいつでも内容を確認できる状態である必要があります。
③周知の要件
「周知」とは、従業員が就業規則の存在や内容をいつでも確認できる状態を指します。具体的には以下の方法があります:
- 休憩室などに備え付ける
- 社内サーバーやクラウド上に保存し、従業員がアクセス可能にする
周知が不十分な場合、就業規則としての効力が認められない可能性があります。
④届出義務
- 就業規則を作成・変更した場合は、管轄の労働基準監督署への届出が必要です(常時10人以上の従業員がいる事業所)。
- 届出を怠ると労働基準法違反となり、罰則(30万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。
私たちFUJITA社労士事務所が全て解決いたします。
主なサービス内容
①就業規則・各種規定の新規作成
- 労働基準法や関連法令に準拠した適切な就業規則を作成します。
- 企業様ごとの特性や課題に応じたオーダーメイド対応。
② 就業規則診断(無料)
- 現在運用中の就業規則を診断し、不足点や改善点をご提案します。
- 法改正への対応状況もチェック。
③ 就業規則の改定サポート
- 法改正や企業方針変更に伴う改定を迅速かつ正確にサポートします。
④ 各種規定作成
- 賃金規程、育児・介護休業規程、ハラスメント防止規程など、必要な各種規定も対応可能です。
⑤ 労働基準監督署への届出代行
- 作成・改定した就業規則を管轄労働基準監督署へ届け出ます。
FUJITA社労士事務所では、お客様ごとの最適な解決策をご提案いたします。
就業規則を整備していると、経営者様にはこんな良い事があります。
1. 労使トラブルの予防とリスクヘッジ
就業規則を整備することで、労働条件や会社のルールが明確になり、従業員とのトラブルを未然に防ぐ効果があります。たとえば、残業や有給休暇、解雇・懲戒処分の基準などを明記しておくことで、「言った・言わない」の水掛け論や不当解雇・未払い残業代の主張を回避しやすくなります。
2. 従業員の安心感・信頼感の向上
就業規則で休暇や手当、ハラスメント防止、安全衛生などのルールを明記することで、従業員が安心して働ける環境を作れます。会社への信頼感や定着率アップにもつながります。
3. 労働条件の明示と業務効率化
共通する労働条件を就業規則でまとめて明示できるため、個別の雇用契約書の作成や説明の手間が減り、業務効率化にも役立ちます。
4. 残業代・長時間労働の抑制
変形労働時間制や残業許可制を就業規則に盛り込むことで、無駄な残業や長時間労働を抑制し、残業代コストのコントロールが可能です。
5. 会社の成長・変化に合わせた柔軟な運用
法改正や会社の成長に合わせて、就業規則を見直すことで、常に最新のルールで経営ができるのも大きなメリットです。最近では、育児介護休業法やパワハラ防止法、月60時間超の残業割増率引き上げなど、法改正に合わせた規則の見直しが重要です。
6. 小規模企業でも大きな効果
従業員10人未満の場合でも、就業規則を作成することで労使トラブル予防や会社の安定運営、従業員との良好な関係構築に大きく貢献します。
7. 就業規則がない場合のリスク
就業規則がないと、従業員の待遇や働き方に不安が生じやすく、トラブル時に会社側の主張が通りにくいなどのデメリットがあります。
まとめ
就業規則は「会社を守る盾」であり、「従業員の安心の証」です。
トラブル予防・業務効率化・信頼感向上・最新法令対応など、多くのメリットがあるため、定期的な見直しも含めて積極的に活用しましょう。
就業規則の作成・変更のご依頼があると、経営者様から固定残業(みなし残業)についてご相談が多いです。
1. 固定残業代制度が有効となるための「三大要件」
固定残業代(みなし残業代)制度は、以下の3つの要件を満たさないと無効と判断されるリスクがあります。
明確区分性
基本給と固定残業代を明確に区分し、金額・時間数を具体的に記載します。
例:「基本給25万円、固定残業代5万円(30時間分)」と明示。「基本給30万円(残業代含む)」のような曖昧な記載はNGです。
対価性
固定残業代が何の対価か(時間外労働、深夜労働、休日労働など)を明記し、対象範囲を明確にします。
差額支払の規定と実態
固定残業時間を超えた場合、必ず超過分の残業代を追加支給する旨を明記し、実際に支払う運用が必要です。
2. 就業規則・雇用契約書・給与明細の「整合性」
すべての書類で内容を一致させる
就業規則、雇用契約書、給与明細のいずれも「名称・金額・時間数・計算方法・超過分支給ルール」を統一し、矛盾がないようにします。
求人票・募集要項にも明記
職業安定法の観点からも、求人票に「基本給」「固定残業代」「対象時間数」「超過分支給」の記載が必須です。
3. 固定残業時間数・金額の「妥当性」と注意点
固定残業時間は原則「月45時間以内」
36協定の上限(月45時間、年360時間)を超える設定は違法リスク。社会通念上も妥当な範囲に抑えましょう。
基本給とのバランス
固定残業代が基本給より高い、あるいは極端に多い場合は制度自体が無効とされるリスクがあります。
最低賃金の遵守
固定残業代を除いた基本給が最低賃金を下回らないように注意します。
4. 制度導入・運用の実務ポイント
導入時は従業員の同意が原則
給与体系の変更(例:基本給減額+固定残業手当新設)は「不利益変更」となりやすく、個別の同意が必要です。
制度導入後も労働時間管理は必須
固定残業代を導入しても、実際の労働時間を正確に把握し、超過分があれば必ず追加支給します。
深夜・休日労働の扱い
固定残業代に深夜・休日労働を含める場合、その旨を明記し、割増率も正確に計算します。
5. 実例・裁判例から学ぶリスク
明確区分性がない場合、全額未払い残業代請求が認められるケースあり(小里機械事件、テックジャパン事件、日本ケミカル事件など)ます。
実態と乖離した固定残業時間数(例:月70時間、80時間)は制度自体が否定されるリスクもあります。
また、求人票や雇用契約書の記載ミスが労使トラブルの火種になることもあります。
6. 固定残業代の計算方法(手当型の場合)
月平均所定労働時間=(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12
1時間あたりの賃金=月給÷月平均所定労働時間
固定残業代=1時間あたりの賃金×固定残業時間×割増率(通常1.25)
【例】
月給30万円、年間休日120日、所定労働時間8時間、固定残業時間40時間
→ 月平均所定労働時間=(365-120)×8÷12=163.3時間
→ 1時間あたりの賃金=300,000÷163.3=1,837円
→ 固定残業代=1,837円×40時間×1.25=91,850円
7. 固定残業のメリット・デメリットの再整理
メリット
給与計算が簡単
人件費の見通しが立てやすい
従業員の収入が安定
デメリット
実残業が少ないと人件費が割高になる場合あり
制度設計・運用ミスで違法リスク
求職者から敬遠される場合もあり
まとめ
固定残業代制度は、就業規則・雇用契約書・給与明細の三位一体で「明確区分性」「対価性」「差額精算ルール」を徹底し、実態に即した妥当な時間数・金額で運用することが絶対条件です